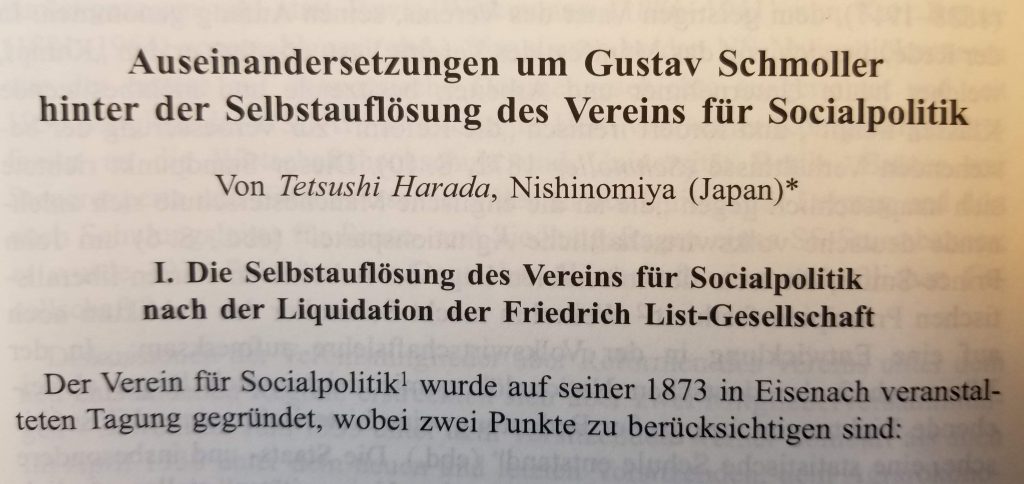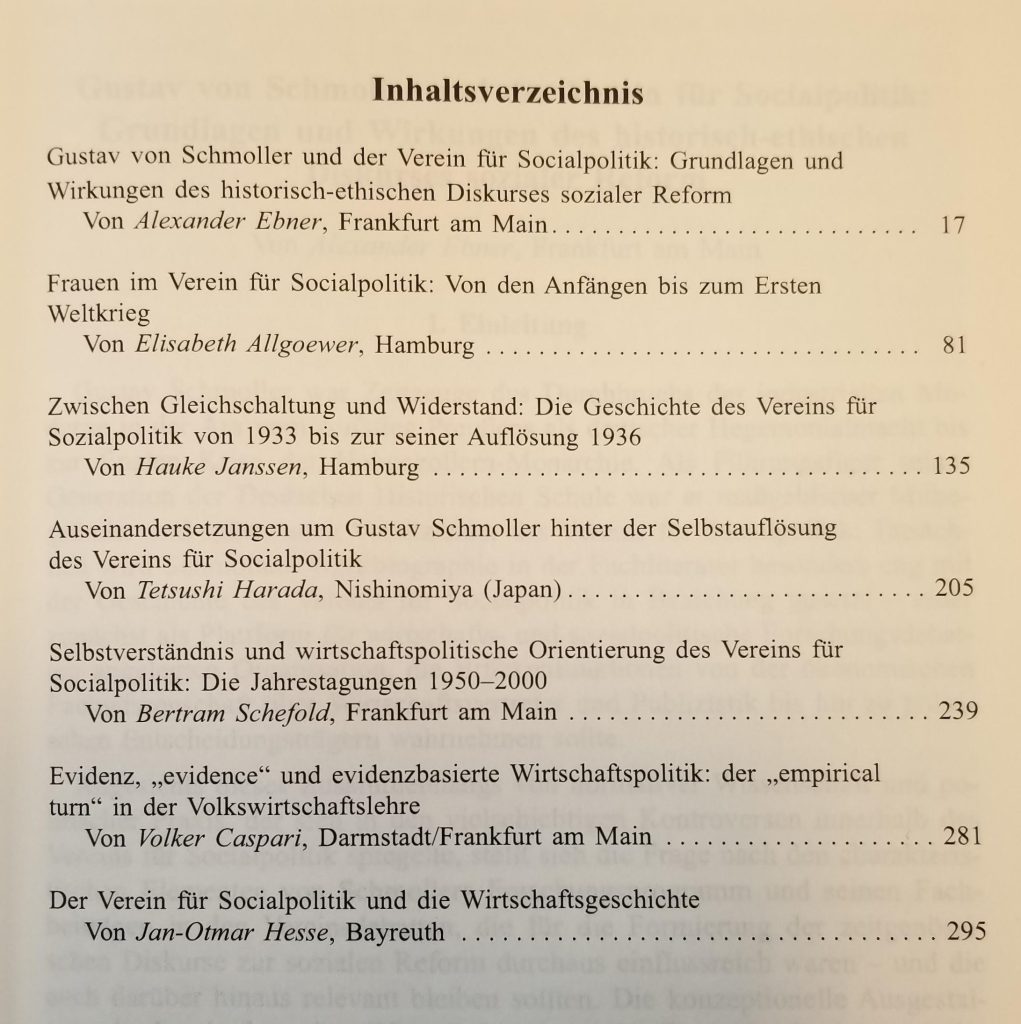論文「社会政策学会の自主解散の背後での、グスタフ・シュモラーをめぐる論争」
各国民の個性を尊重した制度主義的な経済学を構想したとはいえ非体系的で細目研究の寄せ集めともいえたグスタフ・シュモラー(1838~1917年)の歴史学派経済学は、1920~30年代にドイツの社会政策学会(創立は1873年)のメンバー、ヴェルナー・ゾンバルト(1863~1941年)、エトガー・ザリーン(1892~1974年)、アルトゥア・シュピートホフ(1873~1957年)によって手が加えられ、今日でも有効となりえそうなところまで来ていた。
ゾンバルトは「経済システムWirtschaftssystem」構想によって精神(経済心性)・形態(規則と組織)・技術(過程)という3段階で国民経済を特徴づけてそれを体系化した。ザリーンは「俯瞰的理論anschauliche Theorie」の枠組みで合理的・計算的要素と文化的・精神的要素を整理した。シュピートホフは動態的な進化の包摂を試みた。
しかし、そこにナチスが政権を取り、御用学者エルヴィン・ヴィスケマン(1896~1941年)を会長に据えろと要求したのである。
最後の会長のコンスタンティン・フォン・ディーツェ(1891~1973年)は会長職以前には前会長ゾンバルトによる自主解散の提案に反対していた。しかし、自ら会長職に就くと事の深刻さを自覚し、ナチスに乗っ取られてシュモラー経済学のナチス的解釈が学会の方針となるよりも自主解散の道を選び、学会は1936年に解散した。
日本では、金子弘(1898~1964年)がヴィスケマン他編『ドイツ経済学の道』(1937年)を邦訳してドイツ歴史学派のナチス的解釈を提唱した。
しかし、高島善哉(1904~90年)はザリーン『経済学史』第2版(1928年)を邦訳して「俯瞰的理論」を(「直観的理論」と訳して)紹介し、その枠組みを使って、ナチス流の精神主義的な経済思想に対してスミス的な合理的・自由主義的な要素を堅持べきことを説いた。『独逸社会政策思想史』(初版1936年)でシュモラーと社会政策学会を論じた大河内一男(1905~84年)は、ナチスの圧力で社会政策学会が自主解散に追いやられた過程を知らしめて暗に批判した。そして、大河内・高島の後続として戦後の小林昇・水田洋がある。
この論文は、戦後再建された社会政策学会の経済学史委員会(今年7/2の記事を参照)の2022年次集会で、つまり2023年の学会設立150周年記念の共著を準備する集会でなされた原田の報告が、元になっている。なので、今年の8月に刊行された『社会政策学会叢書』の設立記念号(第115巻第41号)共著 ペーター・シュパーン編『社会政策学会の歴史に寄せて』(ドゥンカー & フンブロート、ベルリン)に所収されて出たのである。
長年お世話になっているベルトラム・シェフォールトさん、ハンブルク滞在の受入教授エリーザベト・アルゲヴェアさん、また友人のハウケ・ヤンセンさん(今年7/12の記事を参照)も一緒に、ひとつの本に収まって出せたことは、このうえない喜びである。
ドイツ歴史学派経済学は、とくに1990年代に、新たな制度経済に類似する構想がすでにあったとして クローズアップされたが、その意味はいったいどうだったのだろうか。彼らが強調した制度的・文化的で非数量的な要素と数量的な要素との関連は経済学においてどう捉えるべきなのか。また、学会に政府が介入してそれに抵抗する――あるいは抵抗できなくなる――とはどういったことなのか。これらについての示唆が得られれば、と思って論じた。